Journal
摩天楼とビルマブレンド
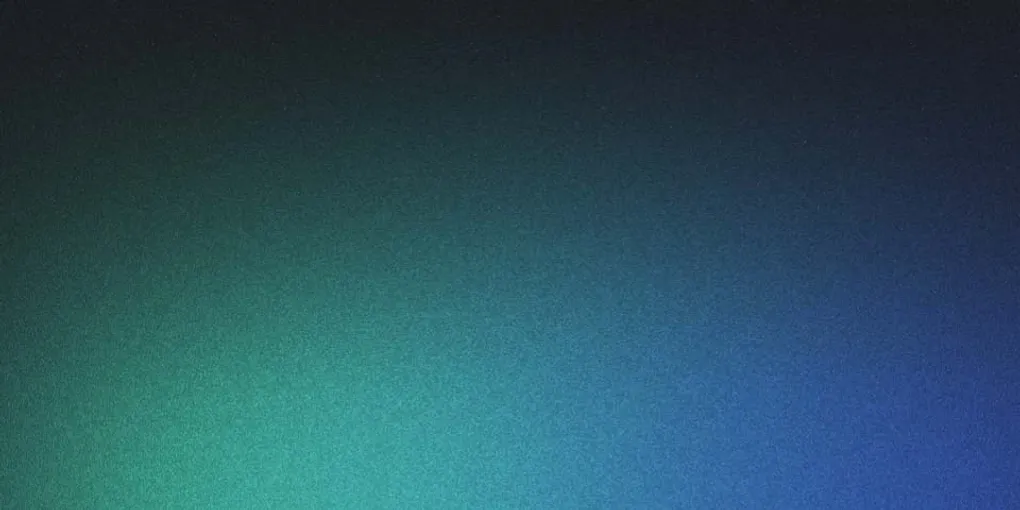
気がつけば、雲ひとつない青空でした。はるか高空に白い太陽が浮かんでいるばかりで、コンクリートの屋上はひどくあついのです。デパートの偉い人も担任の先生も、ハンカチで顔をぬぐっていました。
私は、カーキのがさがさした国民服と、きついゲートルにつつまれたまま、灰色の砲塔を指さす教官を薄目でにらみつけました。さっきからずっと「休め」の姿勢で聞き続けているから、彼のどなり声は全く耳に入っていませんでした。
ゴーンゴーン!
屋上の鐘が、正午の時報を告げました。けれども、昼食がないことはすでにわかっておりました。「つわものは、空腹など気合いで乗り切るべきだ」というお言葉のせいで。工場動員が始まってから、毎日お腹が空いていたけれど、だれもいい出せなかったのです。ハッカ飴が食べたい。ペとっとした甘さと、ツーンとはなに抜けるハッカの香り。
「これより、各班ごとに、高射砲の空砲射撃演習を行う! 配置につけ!」
号令とともに、私たちは先に決められた5人組であつまり、影ひとつない床の上で一列に並びました。屋上の端に積まれた巨大な砲弾を、掛け声とともに持ち上げては、ゆっくりとリレーしていきました。
怒声の中、おぼつかない細い腕が飴色の砲弾を装填すると、ガチリガチリと歯車を回して角度を調整しました。「放て!」の掛け声を聞いて、私はあわてて耳をおさえました。次の瞬間「スポン!」といって、白い煙が吹き上がりました。花火みたいな、カラッとした匂い。
「なあんだ、意外とあっけないな」
誰かがポツンとこぼしました。
銀座の街は、灰色でした。屋上から見下ろす屋根は、どれも空襲避けのコールタールが塗ってあって、シマシマの灰色であふれておりました。ずっと前に見た赤いアドバルーンの記憶。
教官の怒声を横目に、汗でにじんだ紙の表をぼんやりとながめました。「目標まで二千、角度は三十五度……」私は、数字の並んだその表をぼんやりと追いました。気温や風速に応じて、砲の仰角を補正する計算表らしいのです。けれど、どの数値を指さしているのかよくわからず、まぶしさで紙面がにじんで見えました。それに、数字が溶けたりくっついたりして、ゆったりとおどり、ロシア語やアラビア語の新聞に見えたりしました。
「早く、列に並べ!」
その時、コショコショコショとささやき声がして、すうっと空気が冷たくなりました。モノクロームの屋上の隅に、スッとした黒いドレスと、黒い帽子を被った人影が、私の方を向きながら、はだしで突っ立っていました。顔が帽子のつばに隠れて見えないのに、くちびるだけが奇妙に赤いのです。
場面転換。私は、エスカレーターに立っていました。広告も何もないエスカレーター。何も着ていないマネキンばっかり。ショーウィンドウに並ぶマネキンのひとつが、やけに黒くて小さいのです。それは、さっき見た人影でした。モノクロームの彼女は、ものうげな表情をうかべて、胸ポケットから灰色の写真を取り出しました。
「忘れられない。ずっと前に、南の方へ行ってしまったのだけれども」
渡された写真は、端の方がぼろぼろになっていました。映っていたのは、ぎこちないポーズをとる、14歳の少年。大正天皇に似ていました。英国陸軍士官の大礼服を着ていたのですが、威厳はなく、むしろ彼の未熟さばかりが目立ってばかりいました。
いつしかわたしは、白いコンクリートの廊下を歩いていました。どこかの病院のようでした。コーンコーンという靴と、キリキリキリという台車の金切り声。
「もしかしたら、南方で負傷して、帰ってきているかもしれませんよ。ほら、シンガポールなんか、まだ船が通っていましたし」
私は、抜け出した授業の後ろめたさをポケットにつっこんで、黒い帽子に語りかけました。
「いいえ、わたしはね、この写真の主が、もうどこにもいないことぐらいわかります。だってほら……」 「でも、間違いかもしれませんよ」
電話のベルが、チリンチリンと鳴りました。黄銅色のベルがふたつ、目玉のようになっていて、口みたいな受話器がふるえていました。わたしは、「よくない電話だ」と思いました。居眠りしていた白い看護師さんが、赤十字の帽子をあわててかぶり、ガチャリとそれを取りました。
「シーツが足りません。ええ、銀杏通りのふもとのカフェでしょう? 泰緬鉄道のレールに赤い石炭と十字架があって、配給のゴムボールを膨らませた男の子がにわとりの息を詰まらせたなんて、本当?」
ふいにファンファーレがなって、赤い幕がパッと広がりました。黒い水のボートの上から見上げる舞台は、金色のライトで照らされていて、無限に並んだ鵜飼いの松明にゆれていました。
桃色のチュチュがビルの屋上をくるくると軽やかに飛び回り、その足元は、尺取り虫みたいにゴリゴリとした三色旗におおわれていました。
「フィリピンの、乙女がひとーり!」
どこからか号令がかかったとたん、桃色のチュチュをひるがえして灰色の体をした少女がとびおりました。歩道橋から、屋上から、ビルの壁を蹴りながら。そして私は、彼女の脚にまとわりついた白いガーゼに目を奪われましたのです。舞台の上の彼女は踊り続けました。回転したり、ジャンプしたり。管弦楽のゆれにそって、紺碧の空をふわふわと泳ぎました。
「あれは!」
気がつけば、チュチュを着て踊っているのは、あの写真の少年なのでした。灰色の体と肌に、チュチュだけが桃色にゆれていて、その鮮やかなコントラストが胸を焼きました。彼は、同じ14歳だけれども、やっぱり大正天皇ににておられて、ずっと大人びた表情をしておりました。彼は、青く美しきドナウをたゆたいながら、不意にひょっと高島屋のビルを落ちていってしまいました。
スポンスポン! 廃虚になった銀座の廃墟に、ポチ袋のような大きさの空砲が次々と撃ちこまれてまいります。手前に走る白線と、頭上を飛んでいくサイレンの音がかみ合いません。どうやら動く者を狙撃しているようでした。空砲演習。
私は、黒い帽子の少女の手を握って、白い煙幕の下を走り抜けました。
「わたしの、行きつけのスターバックスが、安全です。そちらへ」
山手線を降りると、満員になったホームでした。通り雨なのか、白い水飛沫が屋根からあふれでて、ザワザワと人々の頭を打ちます。ぴゅうと風がふいて、学校指定の靴下がはためきました。つばめの大群が舞い踊り、交差していました。監視カメラの上で、忙しそうに、ひなへエサをやるのです。
恵比寿駅は、南洋諸島を模したつくりになっていました。透明な青い水の上に、熱帯植物が繁茂した島がいくつも浮かんでいて、人々はそういう島をひょいひょいと飛び越えていくのです。丸い電灯がたれさがっていて、あちこちが夜になったり昼になったりしました。
「本日のアイスコーヒーは、ビルマブレンドにございます。マラッカの太陽をたっぷり吸いこんで、結露した水を飲んでくださいませ。しばらくしますと、またひどく雨が降りますので、傘のご用意を忘れずに」
私達は、テーブルにつきました。他にだれも客がいないので、ゆったり座れます。常連と思しき少女はメニューも見ずに「セイロンフラペチーノをひとつくださいな」と注文しました。
私たちは、ブロマイド売りから、さっきの桃色チュチュの少年の写真を買いました。灰色の写真なのに、チュチュだけ毒々しく色がつけてあって、端の方に名前が書いてありました。
「で、この写真はどうするつもり? さっき撮ったブロマイドをお上に届けるの?」
彼女は、好奇心たっぷりの目で私を見つめながら問いました。灰色の雲間から差し込んだ幾筋もの光の矢が彼女の美しい顔にプリズムとなって反射して、私はなぜか少女の高貴な色香にドギマギとしてしまいました。
「これはきっと、舞台のサンドイッチ売りが副業に撮ったものでしょう?じゃあ、まさかカモフラージュのために警察に通報するつもりじゃないと信じていますよね。これは貴重な証拠品となりますから、大事に家まで持って帰りなさいよ。では、今日は夕飯のお買い物をしてから帰りますから」 「まってください。ぼくと、もう少しお話ししてくださいませんか?」
すると彼女は、目の前にいる少年など全くオモチャ同然だとかんづいたらしく、ふふんと鼻で笑って、再び脚を組みました。私はむっとしましたが、相手にすべきはそっちではないと考えなおし、「ええ」と言って向かいの席に腰かけました。
彼女は私より少し年上みたいでしたから、敬語を使うべきでしたが、しかしぼくの中の14歳らしい反抗心がむくむくともたげてきてしまったのです。
「あなたは……そのう……」
私が言いよどんでいるうちに、少女は自分の言いたいことをどんどん口にしていきました。まるで舞台女優のようによく通る声なのです。
「簡潔に言えば、摩天楼と飛行機の劇的な衝突を演じたいというのでしょう? あなた達、普段あまり意識していないでしょうけれどもね」 「なんでそれを?」
私はますます混乱しました。何を言っていいやらわからずにただ目を白黒させることしかできませんでしたが、彼女はさして興味もなさそうに話を続けました。
「でもね、物事はなるべく単純化してしまった方がよろしいのよ。余計なことを考えずにあっさり進めてしまったほうが良い結果が出ることもあるから」
私が何も言えないでいると、少女はさらにミルクのバケツを転がして、あたりは一面に白いシーツの海になっているのでした。はだしのかかとをゆるやかにのばして、彼女は一人シーツの海に浮いておりました。
「もう眠らなければ。でないと、明日が来なくなる」