Journal
風の又三郎とChatGPT
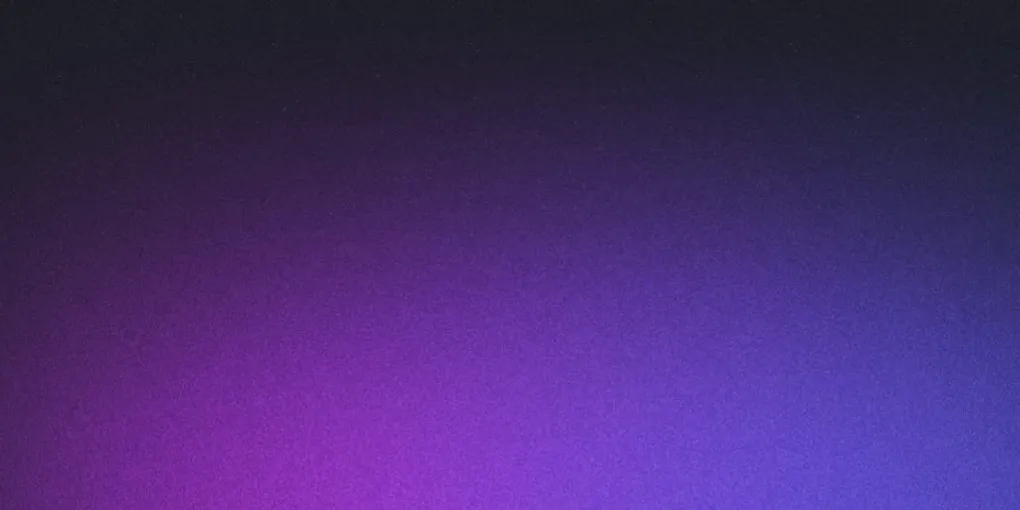
(提出前日に慌てて書いた素人の感想レポートなので、いろいろおかしいです)
わたしは、民俗学を受講する前から、この分野に対して深い興味を抱いてきた。その原点は、幼い頃から親しんできた宮沢賢治の作品群にある。
特に、「風の又三郎」や「グスコーブドリの伝記」「雁の童子」といった作品に魅せられた。イーハトーヴォと名付けられた世界を舞台に描かれる、SFめいた科学ロマニズム、欧州を思わせる異国趣味。時代を越える美的センスで構築されたファンタジーは美しい。
しかし、それと同時に物語の隙間で描かれる、東北の民衆のリアルな生活にも関心を抱いた。
ちょうど同じ時期、わたしは柳田國男の「遠野物語」に出会った。岩手県花巻の出身である宮沢賢治が、遠野郷で収集された民話に影響を受けたという背景を知った時、わたしの興味は民俗学へと傾倒した。柳田國男の『遠野物語』や『海上の道』、『豆の葉と太陽』、『日本人』を読み進め、最終的に柳田の全集を通じて民俗学への深い興味を抱くに至った。
わたしの母が、南九州や日本海沿岸における風俗・民家・信仰に詳しく、家庭内でも民家採訪の記録や地域の風習について記述された本が身近にあり、幼年期から自然とそれらにふれてきた背景もある。
こうした経験から、日常生活においても、その地域の風習に関して自然と意識を向ける習慣が身についたのかもしれない。今回の発表テーマである「東北の土着信仰」は、班員のAくんからの提案であったが、わたしの長年の興味関心のルーツと深くつながるものであった。
今回の民俗学の講義を通じてもっとも印象に残ったのは、人間と衣服の関係性について、その多角的な意味合いを学べたことだ。衣服とは、単なる機能的要請によって生まれた実利的な産物ではなく、そこには社会的な役割を示すアイコンとしての働きが多分にある、という点だ。
このことを象徴的に示したのが、白いシャツを手に入れた祈祷師の話だ。その祈祷師は、手に入れたばかりの白いシャツを、あえて灼熱の昼間に着込み、肌寒い夜には脱いでしまうという奇妙な行動をとった。
このエピソードは、祈祷師が文明からもたらされた白いシャツを、実用的な衣服としてではなく、「祈祷師」という自らの役割を強調し、その存在を周囲の村人に誇示するために着用したのだ、と解釈できる。これは、衣服が単なる布ではなく、社会的な役割や地位、あるいは精神性を象徴する「記号」として機能していることを示している。
この傾向は、理性的と言われる現代社会においても見られる。日本では、高温多湿の真夏にも関わらず、長袖のフォーマルなスーツを着るビジネスマンが多数見受けられるし、カジュアルな私服であっても、長ズボンを履く傾向が強い。
実利面から考えれば、半ズボンや、着流しの「しぼり」・「ちぢみ」地の浴衣などの方が、どう考えても身体への負担が少ないはずである。それにも関わらず、われわれは、文化的・社会的なコードに従って、真夏でもあつい長ズボンや、風の通りづらく蒸れやすい筒袖のTシャツを着ている。
これは、衣服が機能性だけでなく、社会的な意味合いや規範によって選択されていることの表れであり、民俗学的な視点から見れば非常に興味深い現象だ。
わたしは、班活動を通じて、「東北の土着信仰」の中でも特に「風の三郎伝説」について深く調べた。「風の三郎」は、新潟県および東北地方で信仰される風の神である。立春から数えて210日目(9月初頭)など、台風が多い時期に農作物を風から守ってほしい、という民衆の願いから信仰されてきた。
この伝説を調査する中で、改めて宮沢賢治の童話「風の又三郎」が持つ意味合いについて考察した。宮沢賢治は、「風の又三郎」において、白い洋服を着た風の神の少年として、この三郎神を描いた。
作中、怪異の対象であった「又三郎」は、地元の少年たちと明らかに異なる服装をしていた。他の子どもたちが浴衣や袴であったのに対し、転校生である「又三郎」は、札幌から来た都会的な少年として、白いシャツと半ズボン、ねずみいろのジャケット、帽子を着用しており、言葉も東北方言ではなく標準語であった。
現代の感覚からすれば、彼の格好や行動には何の違和感もない。しかし、作品の舞台が1920年代から1930年代の東北の農村だということを考慮すると、彼の異質さは際立っていたと言える。
三郎を見た子どもたちが、地域に伝わる信仰のひとつである「三郎伝説」と結びつけて、彼を怪異として認識・記憶するのも当然のことであったと思われる。
宮沢賢治の「風の又三郎」に見られるように、人間が理解し難い「異質」なものに直面した際、わたしたちは、既存の文化的枠組みや「テンプレート」に当てはめて解釈し、受容しようとするメカニズムを持っていることに気付かされる。
又三郎の異質な服装や言葉遣いが、農村の子どもたちに「三郎伝説」と結びつけられ、「怪異」として認識されたのは、まさにこのシステムが働いた結果と言えるかもしれない。土着信仰は、自然現象や不可解な出来事を「神」や「妖怪」といった形で解釈し、異質なものと共生するために生活の中に組み込むための枠組み、あるいはインターフェースとしての役割を果たしてきたのかもしれない。
さらに考察を広げると、このような「文化的テンプレート」を利用して異質なものを受容しようとする傾向は、日本文化全体に深く根ざしているのではないかと感じる。
例えば、神道と仏教という二つの異なる宗教体系が混在して存在し、お互いに影響し合いながら融合してきた「神仏習合」の歴史は、その典型であろう。また、「ドラえもん」に代表される親しみやすいロボットや、初音ミクをはじめとするヴォーカロイド、「ChatGPT」に象徴されるバーチャルな人工的存在を、わたしたちが何の抵抗もなく、むしろ親しみを持って受け入れている現象も、この特質と無関係ではないはずだ。
これは、外来の文化や新しい技術を柔軟に取り入れ、自分たちの生活に調和させてきた日本人の高い受容性が生み出した、独自のシステムと言えるかもしれない。
この日本文化における受容性は、今後さらにわたしたちの日常生活に浸透してくる大規模言語モデルといった、異質な存在をわたしたちがどのように受け入れていくか、その鍵を握る極めて重要な性質である、とわたしは考える。
わたしは、民俗学の授業を通じて、人間と技術の関係性を考える上で基本的な視点を学ぶことができた。今後も技術者として、ただ技術について考えるだけでなく、その役割や作用、社会的な立ち位置なども考慮にいれて、学び続けていこうと思う。